- 特養とグループホームの業務内容は何が違うの?
- グループホームの食事は介護職員がつくるの?
- 夜勤者はひとり?何かあったらどうするの?
特別養護老人ホームからグループホームへ異動・または転職する時に、このような不安があります。同じ介護現場であっても、業務内容に違いがあります。
しかし、事前に違いと対応方法を知っておけば困らずに済みます。

- 長期55名と短期20名の特養の生活相談員から
- グループホームの管理者、計画作成担当者、生活相談員、介護職員(すべて兼任)へ異動経験あり
- 特養は長期55名と短期20名の従来型多床室の施設、グループホームは利用者9名1ユニットの施設
以上の条件で異動した経験をもとにして
- 特養とグループホームの業務内容の違い
- 食事づくり
- 夜勤者ひとりでの対応方法
以上の内容について説明をします。
特別養護老人ホームとグループホームの業務内容の違い

比較する前に施設ごとの利用者やスタッフの違いを確認しておきます。
法人また事業所によって利用者定員やスタッフ数、配置職種などに違いがあると思いますが、ここでの比較はこの状況を前提として解説していきます。
| 特別養護老人ホーム 従来型(個室・多床室) | グループホーム 1ユニット | |
|---|---|---|
| 利用者数 | 長期入所55名・短期入所20名 合計75名 | 利用者9名 |
| スタッフ数 | 生活相談員 1名 介護職員 30名 看護職員 4名 介護支援専門員・機能訓練指導員 など | 管理者 1名 (生活相談員) (計画作成担当者) (介護職員) 介護職員 7名 |
| 勤務者数 | 日中の勤務者数 10〜13名 夜勤者数 3名 | 日中の勤務者数 2〜3名 夜勤者 1名 |
利用者の数が違う
- 特別養護老人ホーム:長期入所55名と短期入所20名の合計75名
- グループホーム:9名
事業所の規模として当然ですが、利用している利用者数、居室の部屋数やトイレの数、また食堂や浴室など場所や建物そのものの広さが違います。
特別養護老人ホームのメリット
- 様々な身体状態や認知症症状の利用者を対応するため、技術と知識が実践で身につきやすい
- ベッドやセンサー、リクライニング車椅子など、様々な介護機器を扱う機会が多い
- 相性が良くない利用者と距離をとることができる
要介護度が支援1から要介護5までと幅広く、また身体状態や認知症症状、健康状態や疾患なども多様な利用者の介助を行うことになるため、食事介助や移乗介助などの身体介護の技術なども、実践を通して習得することができます。また、認知症症状の対応についても、様々な事例の対応にあたるため、広く知ることができます。
様々な状態の利用者がいるため、その状態に適した環境となるように、いろいろな種類の介護機器があります。車椅子の種類も、標準タイプからモジュールタイプやリクライニングタイプなどを実際に使用します。また、センサーやベッド、また移乗時の介護リフトなどの機器もあるため、業務を通じて様々な介護機器に触れる機会があります。
多くの利用者がいるので中には相性が合わない利用者もいます。もちろん必要な介助は行いますが、他の利用者への介助もあるため、適度に距離を取りやすくなります。
グループホームのメリット
- 既往歴や細かな介助方法、家族構成などの個人の情報を覚えやすい
- フロア全体に目が届き、見守りがしやすい
- 利用者と密な関係が築きやすい
利用者が少ないと必要な情報も覚えやすくなります。75名と9名とでは覚える情報量はかなり違います。個々の状態に適した介助を行うためには、情報を把握する必要があります。利用者数が少ないと細かな情報も頭に入れておくことができ、丁寧に関わりやすいです。
9名の生活空間なので、リビングからすべての居室やトイレ、浴室や洗濯室など、フロア全体に目が届く広さになっています。従来型特養の施設と比較すると建物の広さは明らかに違い、廊下の向こう側の居室に走っていくこともなく見守りができます。
勤務中は9名全員に関わることになり、介助する頻度も多くなります。より利用者の状況が把握でき、関係を築きやすくなります。
スタッフの数が違う
- 特別養護老人ホーム:介護職員30名・看護職員4名・生活相談員1名・介護支援専門員1名・栄養士・調理員など
- グループホーム:管理者・計画作成担当者・生活相談員・介護職員 合計7名
利用者数が違うのでそれに関わるスタッフ数も違います。
特別養護老人ホームのメリット
- 他の職種のアドバイスや協力が得られる
- 職種間でのスキルアップが図りやすい
- 相性が良くないスタッフと距離をとることができる
介護職員だけでなく、看護職員や栄養士、調理員などの他の専門職もいるため、自分ではわからないことも他の専門職にきくことで、知識や技術を知る事ができます。
特に看護職員からは、医療に関する知識を通常の業務を行いながら教えてもらうことが多いため、実践的な知識を学習することができます。
同じ職種の中で知識や技術を共有して高め合えることができます。介護職員など、人数が多いと外部研修を受ける機会も増えます。学んだことを持ち帰ることで、他のフタッフにも同様の学びの機会を作ることもでき、スキルアップの機会も多くなります。
相性が合わないスタッフも中にはいます。多人数のスタッフがいるからこそ、距離をとりながら仕事をすることもできます。同じ勤務になることはあっても、2人きりになるという状況はあまりないので、気まずくなることも少ないです。
グループホームのメリット
- スタッフ間での情報共有が迅速かつ確実にできる
- スタッフ同士が密な関係をつくりやすい
スタッフの人数が少ない分、小回りが効きます。連絡事項などの周知も、検討課題の共有も迅速にでき、直接口頭で確実にできるため、漏れがありません。
話をする機会が多くなるということは、意見交換なども通じてよりお互いを知ることになります。そのため、信頼感を強くすることができます。
勤務者の数が違う
- 特別養護老人ホーム:早出3名・日勤1名・遅出3名・準夜勤3名・夜勤3名
- グループホーム:早出1名・日勤1名・遅出1名・夜勤(16時間)1名
スタッフの数が違うのでシフトを組んだ場合の人員配置も違いますが、利用者の人数も踏まえて考えると、1名の介護職員に割り当てられる利用者数にも大きな差が出てきます。
特別養護老人ホームの場合は、日中で早出と日勤と遅出と準夜勤の勤務が重なる短時間に10名〜13名ほどの勤務者が揃いますが、時間帯によりかなり変動します。
例えば朝食時は夜勤者3名と早出3名、後から日勤者が加わりますが、夜勤者の勤務が終わると早出3名と日勤者1名で遅出の出勤まで対応することになります。
夜勤者3名に対して利用者75名と、スタッフ1名あたり利用者25名の割り当てになり、仕事量は多いです。
このように時間によって勤務者数も変わるので、限られた勤務者で対応することになります。
グループホームの場合は、夜勤が16時間勤務なので早出と遅出と重なる時間が多くあります。19時30分から7時までは夜勤者1名での勤務になりますが、その時間以外は最低でも2名の勤務者がいます。
1名になる時間帯はありますが、それでも9名の利用者数を考えれば、人数に対する仕事量は特養よりは軽いと言えます。
グループホームでの食事づくりは介護職員の業務

特別養護老人ホームでは移動介助や排泄介助、入浴介助に食事介助などを行いますが、食事をつくる「調理」は調理員という職種が担ってくれていたので、介護職員は行いません。
しかし、グループホームでは調理員や栄養士は基本いません。管理者・生活相談員・計画作成担当者・介護職員が行います。
- 献立は特別養護老人ホームと同じ献立なので考える必要はなし
- 食材の発注はグループホームの食材発注係が毎日行う
- 朝食は早出、昼食は遅出、夕食は夜勤が約1時間ほどでつくる
- 利用者と一緒に調理ができるのは、調理に余裕のある上級者のみ
献立は同じ法人の特養と同じものなので、考える必要はなく1ヶ月分の献立表を使用します。
各献立ごとに使用する食材料の一覧もあるので、その表をもとにして9名分の食材料を業者に発注します。野菜などの生鮮食品、また肉類は毎日町内の商店から、冷凍食品などは定期的に配達してもらいます。
グループホームでは利用者と一緒に調理を行う、という事業所もあると思いますが、自分に余裕がないと利用者に何を頼むのか判断し、危険のないように見守りをして、かつ自分の調理も行うことは無理です。なので、慣れないうちはまず自分ができるようになることを優先していきましょう。
「食事をつくる」このことを一番の不安に感じる人も多いと思います。結論からいえば、「大丈夫、できます」です。時間は少しかかりますが、できるようになります。
調理する時のポイント
- 先輩職員から手順を教えてもらう
- スライサー・ピーラー・キッチンバサミを使う
- 蒸す・茹でる時は電子レンジを使う
- だしの素で最初の味付けをする
- 前もって作り方を調べておく
主菜・副菜・汁物など複数の品数をつくる時、時間がかかる工程から取りかかるようにしないと、時間がかかります。そのため、先輩から調理の手順を教えてもらい、何から取りかかるのかを習得します。
食材をカットする時、包丁の使い方に慣れていないと時間がかかります。なので、大根やじゃがいもなどの皮を剥く時はピーラーを使い、スライスや千切りをする時はスライサーを使い、肉を切る時やネギをきざむ時はキッチンバサミを使うと、比較的早くカットすることができます。便利な調理器具もあるのでうまく活用しましょう。
野菜類も加熱処理をするので、トマトも湯煎し、キャベツも加熱します。その時に、電子レンジを使って加熱調理をすると、時間も短縮できます。
煮物などの味付けも難しいと思っていました。確かに簡単ではありませんが、まずだしの素を使用してから、砂糖・醤油・みりん・酒などで味を整えるとうまくできます。
前もって自分が担当する献立はわかっているので、勤務に入るまでに料理アプリやサイトで作り方の工程を動画で確認していきます。イメージがある方が手順を組み立てやすいです。
夜間はひとりで勤務する
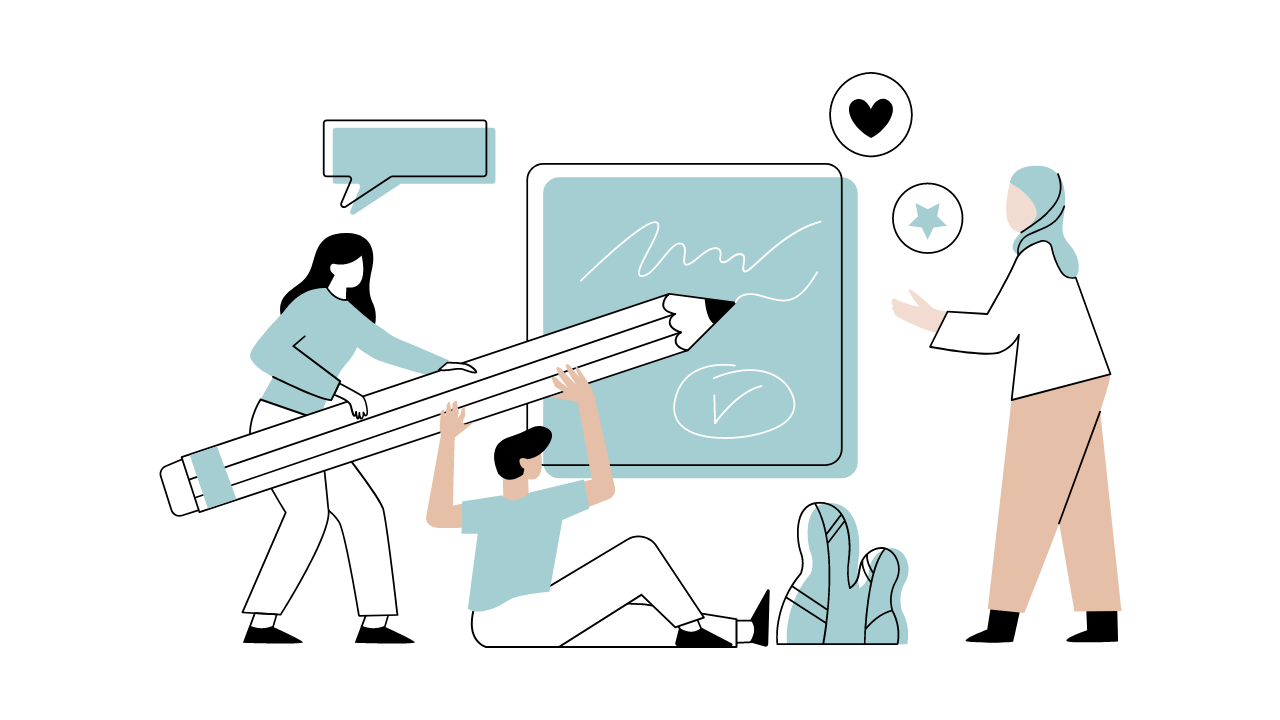
9名のユニットであれば夜勤は1名です。19時30分に遅出が退勤してから、7時に早出が出勤するまでの11時間30分の間は、他の人のケアを頼むこともできませんし、どうしよかと相談することもできません。
夜間のひとりでの勤務で心配・不安なこと
- 介助中に他の利用者からのコールにすぐに対応できない
- 体調不良時や急変時の対応
以上のような心配や不安があると思います。
複数の介助が重なるときは優先順位をつける
9名全員に同時に何か起こることはまずありませんが、トイレでの排泄介助時に居室からコールがある、このような状況はよくあります。ひとりなので誰かがコール対応をしてくれるわけではありませんので、優先順位をつけて対応します。
- 今、介助している利用者のそばを離れること
- コールのあった利用者に待ってもらうこと
これを瞬時に比較して、どちらを優先するべきかで行動します。利用者にもよりますし、経験値のよって変わっていきますが、優先順位をつけて行動します。
急変時の対応は手順を決めておく
意識がない、転倒して動けないなど、急な体調不良や急変時が起こった場合を考えると、とても不安になります。しかも、起こるときは前触れもなく急に起こる場合が多いです。
もし意識がない状態を発見したら…もし転倒して動けない状態になったら…を想定して、どのように対応することができるか、対応すべきかを前もって訓練しておきます。
意識はあるが怪我をしている、体調不良の症状がある場合
- 怪我の部位や体調不良の症状の詳細を確認する
- 上司に報告し医療機関の受診について相談する
- 家族へ連絡し医療機関の受診を相談する
- 受診をする場合は、病院までの搬送方法を相談する(家族に連れて行ってもらう、救急車を要請する)
- 経過をみる場合は、起こりうる急変について家族へ説明して理解を得る
意識なく心肺停止の場合
- AEDと電話を取ってきて、すぐに心肺蘇生を行う
- 119へ電話(スピーカー)をかけ、AEDを装着しながら心肺蘇生を行う
- 家族・上司へ連絡し救急車を要請したことを伝え、すぐにきてもらうように依頼する
- 心肺蘇生を続ける
- 救急隊員が到着後は指示に従う
- 救急搬送の付き添いは家族に依頼する(夜勤者は施設に残る)
以上のように急変時を想定して行動の手順を書き出し、実際に訓練を行うことで、漠然とした不安は少しは解消されます。また、こうした方がいいという改善点も見えてきます。
毎年1回は必ず訓練を行い、手順を確認することを習慣にしていきましょう。
まとめ
人事異動で新しい部署への異動は不安もありますが、新しい体験をすることで自分自身の経験値が増えることは間違いありません。自分の経験値を高め、引き出しの数を増やす機会があれば、挑戦してみましょう。
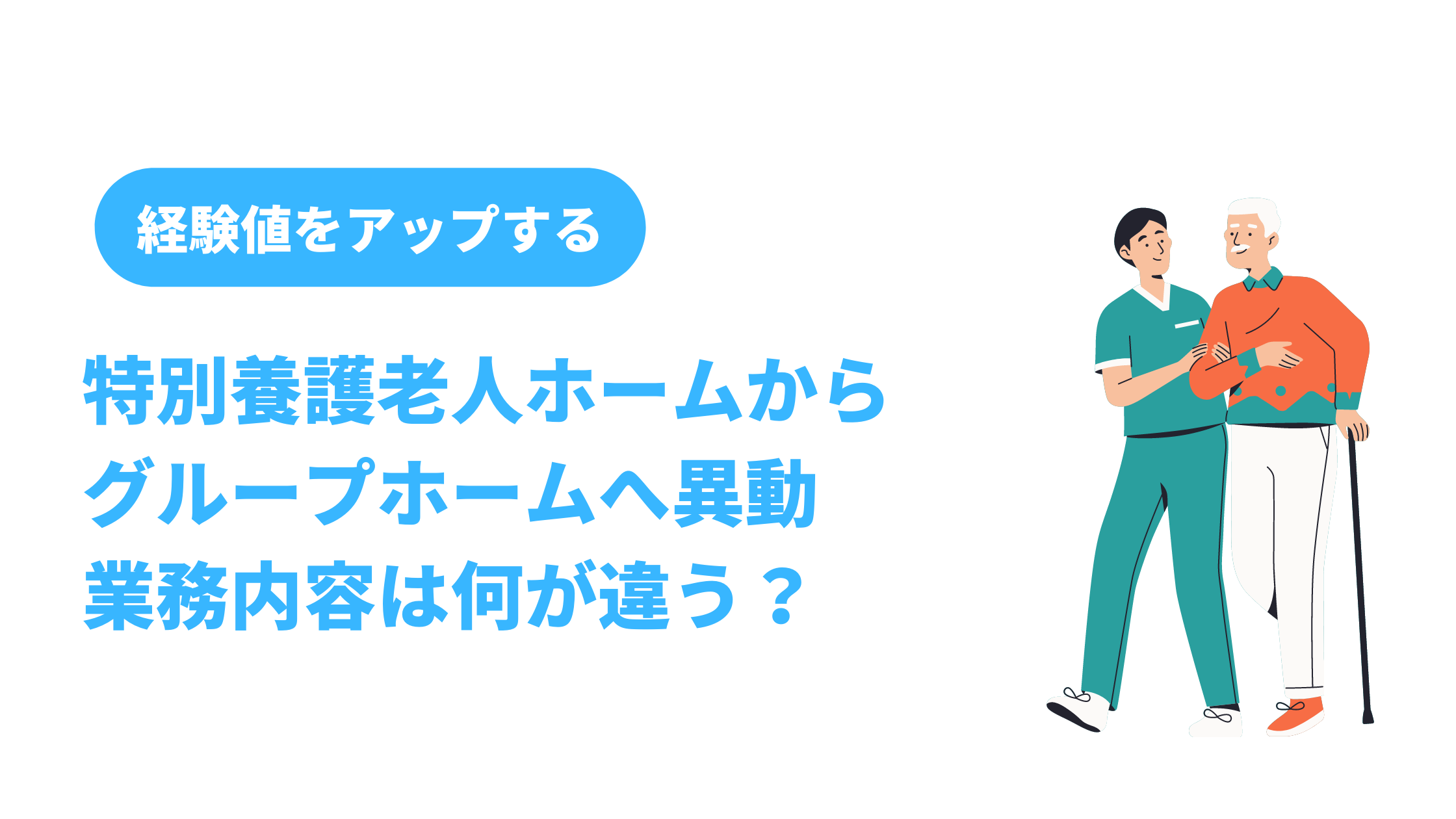


コメント