- どんな時に救急車を呼べばいいいの?
- 119番に電話をかけると何を聞かれるの?
- 救急車が来る前に何をすればいいの?
施設に入所している利用者、デイサービスやショートステイの利用者などに急変があった場合、救急車を呼ぶという場面は必ずあります。
しかし救急車を呼ぶ時、何を言えばいいの?と戸惑うことがあると思います。
前もって聞かれる内容や答え方を知っておけば返答の準備もできますし、必要な資料や物品なども整えておくことができます。
わからないという不安は、仕組みや手順を知ることで軽減できます。
この記事では、救急車を呼ぶ時の手順を説明します。
救急車を呼ぶ時の手順のポイント
- 救急車を呼ぶ症状や状態をスタッフで共有しておく
- 119番の電話で聞かれることを事前に確認しておく
- 救急車が到着するまでに必要な準備をしておく
救急車を呼ぶべき症状や状態をスタッフで共有する

一言で「急変」と言っても起こりうる事態はいろいろあります。
この症状・この状態の時には救急車を呼ぶ方が好ましい、ということをあらかじめスタッフで共有しておきます。
救急車を呼ぶべき症状・状態
- 意識がない(呼びかけに返事がない、反応がない)
- 呼吸をしていない(胸部・腹部に動きがない)
- 体に麻痺がある、嘔吐している
このような時は一刻を争う状態のため、急いで救急車を呼ぶようにしましょう。
意識がない
呼びかけても返事がない、刺激を与えても反応がない場合は、脳疾患などの重大な病気が原因としても考えられます。
直前に転倒などがあれば外傷によるものと考えられますが、そうでなければ疾患による可能性が高いです。一過性のものかもしれませんが、早急に病院へ搬送する必要があります。
呼吸をしていない
呼吸が止まると、酸素が取り込めず心停止となり、血液の循環ができないため脳にダメージを与えることになります。
しかし、施設などで急変時に呼吸の有無を確認することは意外に難しいです。
急変の時は慌てて対応するため、周りに集まったスタッフで騒がしくなり、呼吸の音も聞き取りにくくなります。
また、服を着ている状態だと胸部・腹部の動きがわかりにくく、特に腰が曲がって仰向けができない場合は動きが目視で確認しにくくなります。
- 胸部と腹部が目視できるように服を上げる
- 足を布団などで挙上して仰向けの姿勢をとる
確認できる、確認しやすい状態を確保します。
この状態ではすぐに心肺蘇生を行い、AEDを使用する必要があります。
現在は人工呼吸は省略して胸骨圧迫を続ける方法も示されているので、状況に応じた方法で行います。
心肺蘇生法の手順については下記のサイトで紹介されています。
体に麻痺がある・嘔吐している
このような症状であれば、脳卒中(脳梗塞・脳出血)が疑われます。
体の麻痺・言語障害・嘔吐などの症状もあるので、意識があるから大丈夫ではなく、早急に処置を受けてもらう必要があります。
時間が経つと後遺症が重症化する恐れがあります。
看護師の判断・指示に従う
特別養護老人ホームやデイサービスなどには看護師が配置されているので、急変があればまず看護師が対処することが多く、看護師から指示を受けて救急車を呼びます。
しかし、看護師が施設にいない時間帯も出てくるので、やはり介護スタッフも基本的な知識と技術を身につけておくことは重要です。
グループホームなどには看護師は配置されていませんので、介護スタッフが判断することになります。
119番に電話をかけると何を聞かれるの?
119番に電話をかけると以下のようなやり取りを行います。
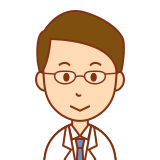
119番です。火事ですか?救急ですか?
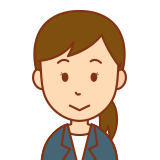
救急です!
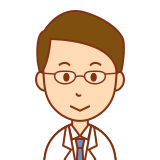
住所はどこですか?
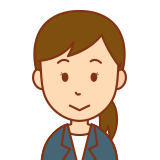
○○市○○町○○の特別養護老人ホーム○○です
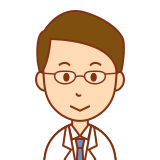
どうしましたか?
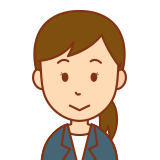
- 利用者がぐったりして呼びかけにも返事もなく、意識がないです
- 利用者が食事中に喉詰を起こしたようで、呼吸をしていないです
- 利用者が右半身に麻痺があり、呂律も回っていません
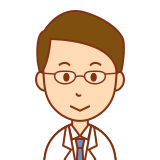
歳はいくつですか?
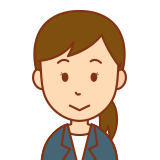
70歳代の女性です
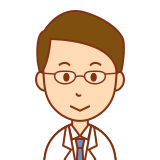
あなたの名前と連絡先を教えてください
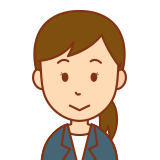
私の名前は○○です
電話番号は○○ー○○です
- 焦らず慌てず落ち着いて答える
- 自分の施設の住所と電話番号を答えられる
- わからないことは「わかりません」とはっきり言い、時間をかけない
意外と自分の勤務先の住所と電話番号を覚えていないスタッフも多くいます。電話の近くなどに施設の住所と電話番号をわかるように明記しておくと、慌てて出てこない時に助かります。
また、利用者の年齢などすぐに出てこない場合は「80歳代です」など大まかで良いです。救急隊が到着後に詳細な情報提供を行えば、問題はありません。
救急車が到着するまでに行うこと
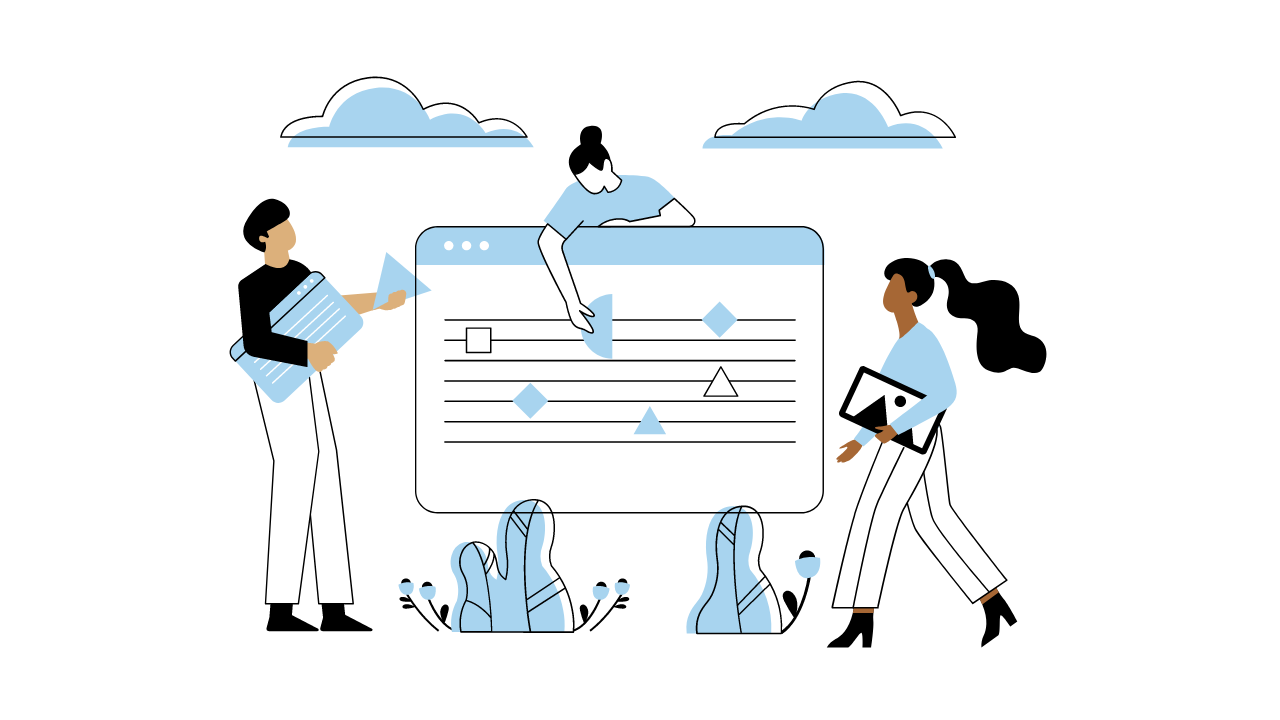
心肺蘇生を行いAEDを使用する
呼吸停止・心肺停止している場合は、心肺蘇生を実施してAEDを使用します。
心肺蘇生は基本的には複数名で行うようにします。
しかし、グループホームなどでは夜勤中であれば1人で行う場合もあると思います。
救急隊員への情報提供を準備する
利用者情報を救急隊員に伝えられるように準備も必要です。
- 氏名、生年月日、住所
- いつ頃から、どのような状態になったか
- 普段の様子やADL
- 既往歴、処方薬、かかりつけ医
- 家族の連絡先
速やかに情報提供できるように書式を準備しておき、必要であれば書類を渡せるようにしておくと慌てずにすみます。
救急車が到着してから行うこと

玄関前で救急車を誘導する
救急車が施設の玄関に到着した後は速やかに利用者の元まで案内します。
- 玄関前で大きく手を振り救急車を誘導する
- 救急車から降りてきた救急隊員と利用者の元へ向かう
- 今の容態(意識や呼吸の有無など)を救急隊員に伝える
- エレベーターを使用する場合は入口を開けておく
- 他の利用者を誘導して救急隊員の通路を確保する
以上のことを利用者の元まで誘導する時に気をつけます。
救急隊員に利用者の情報提供を行う
利用者の元に到着後は、救命処置は救急隊員が引き継いでくれます。
事前に用意した情報提供を行い、到着までに行った処置を説明し、救急隊員とやり取りをします。
落ち着いて事前に準備をした情報提供を救急隊員に伝えます。
救急隊員が容態を確認し、搬送先の病院と交渉して受け入れ病院が決まります。
いざという時に慌てないために訓練をしておく
9月9日の救急の日に合わせて行われる救急救命講習などを受講し、AEDの使用方法や心肺蘇生法のやり方を習得しておくことはとても重要です。
講習会などでは基本的な手順についての講習を受けますが、要介護状態の高齢者を対象にする場合とはまた違ってきます。
まずは講習を受けて基本的な心肺蘇生とAEDの使用方法を身につけ、事業所の中で起こりうる状況を想定した訓練を行うことが効果的です。
- 食事中、気がついた時には顔色が真っ青で呼吸をしていない
- 深夜の巡回時に声をかけたが意識、反応がない
- 車椅子から転落して、頭部を裂傷して出血がある
実践的な訓練を行うことで、いざという時の実践力が向上します。
まとめ
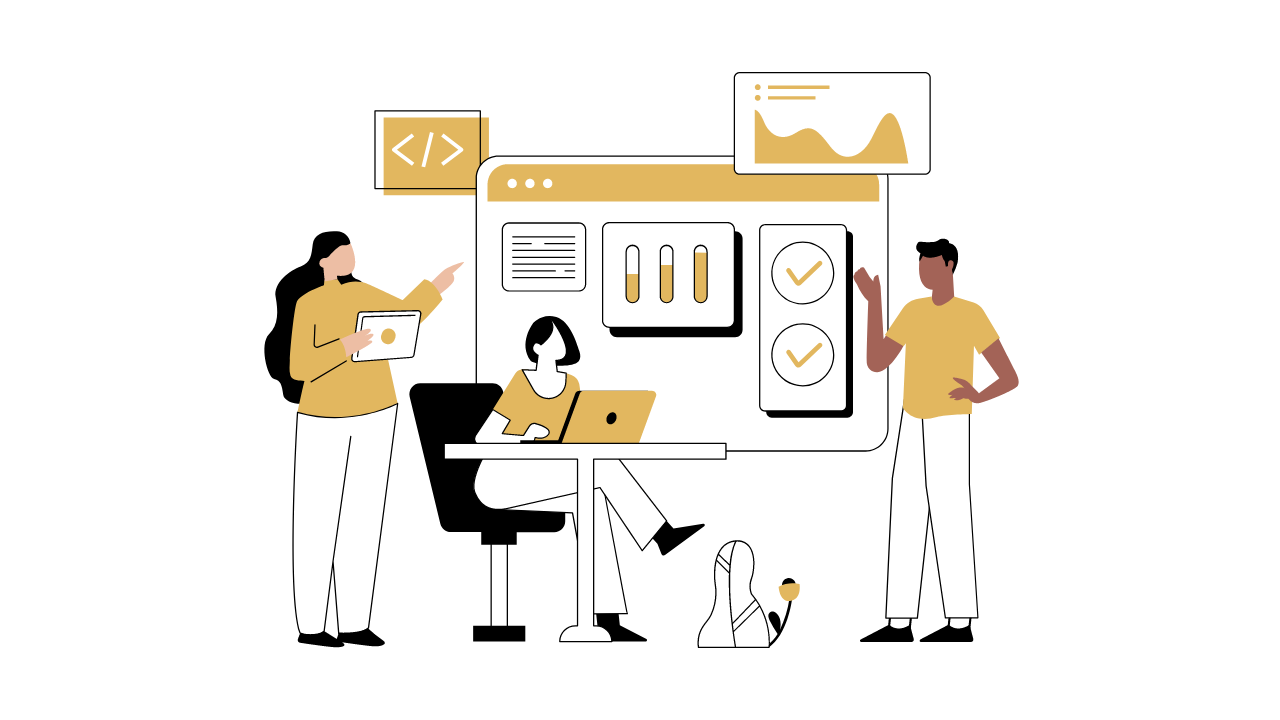
- どのような状態で救急車を呼ぶかスタッフで共有しておく
- 意識がない(呼びかけに返事がない、反応がない)
- 呼吸をしていない(胸部・腹部に動きがない)
- 体に麻痺がある、嘔吐している
- 看護師の判断、指示に従う
- 119番の電話で聞かれることを事前に確認しておく
- 火事ですか、緊急ですか
- 住所はどこですか
- どうしましたか
- 歳はいくつですか
- あなたの名前と連絡先を教えてください
- 心肺蘇生を行いAEDを使用する
- 救急隊員への情報提供を準備する
- 利用者の氏名、生年月日、住所
- いつ頃から、どのような状態になったか
- 普段の様子やADL
- 既往歴、処方薬、かかりつけ医
- 家族の連絡先
- 玄関前で救急車を誘導する
- 玄関前で大きく手を振り救急車を誘導する
- 救急車から降りてきた救急隊員と利用者の元へ向かう
- 今の容態(意識や呼吸の有無など)を救急隊員に伝える
- エレベーターを使用する場合は入口を開けておく
- 他の利用者を誘導して救急隊員の通路を確保する
- 救急隊員に利用者の情報提供を行う
- 事前に準備した利用者情報を伝える
- 救急隊員が到着するまでに行った処置を説明する
- 救急車に同乗して付き添う(状況に応じて)
以上が救急搬送時に行う手順です。
まずは慌てすに落ち着いて行動することが重要です。そして、そのためには訓練を通じて体験を重ねる必要があります。
何度も体験して経験することで行動も伴ってきます。
以下の書籍が高齢者の救急対応についてわかりやすく解説しています。図解で手順を確認でき、気をつける症状についても詳しい説明があるので、おすすめの書籍です。
知識として理解し、訓練を通じて実践を可能にできるようにしていきましょう。
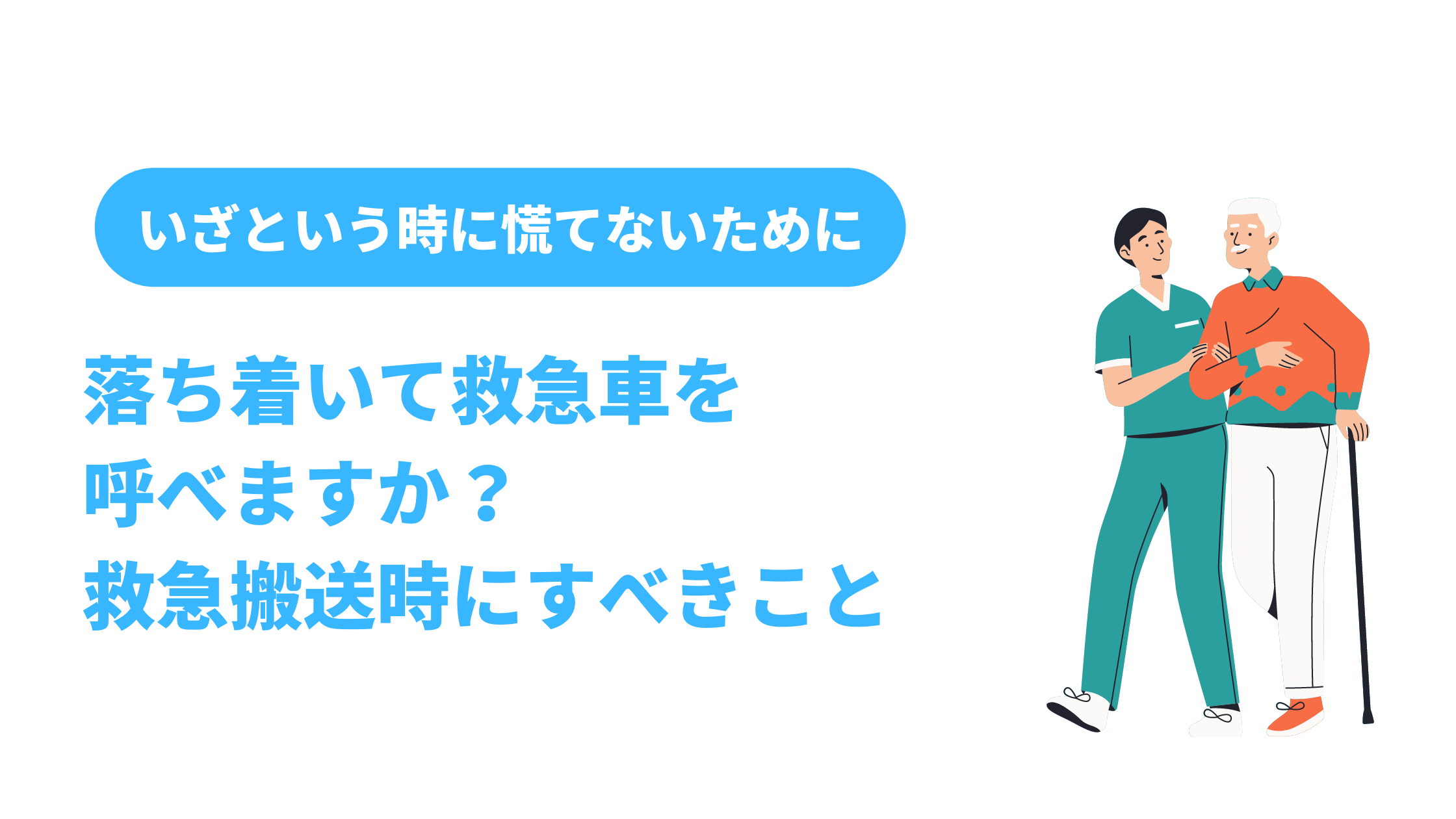


コメント