- 介護リーダーの仕事ってなに?
- 介護リーダーって大変そう…
- 介護リーダーになるためにはどうすればいいの?
介護職員として現場で業務して、リーダーにならないかと話を受けて、評価されての昇進!
でも、介護リーダーって何をすればいいの?私にできるの?と最初は誰もが思います。
前任者のリーダーから引き継ぎも受けるでしょうが、リーダーの業務内容や考え方など習得することがたくさんあり、不安になり悩むこともあります。
リーダーの仕事内容を知り、リーダーに求められる能力・技術を身につけていけば徐々に不安も減ってきます。
この記事では、リーダーが担っている業務内容を説明します。

- 特養で介護副主任を2年、介護主任を3年の経験あり
- 新入職員の育成プログラムの作成と実践を行う
- 介護福祉士実習指導者資格を持ち指導経験あり
リーダーの業務内容
- 介護方針の決定
- スタッフの業務管理
- スタッフの育成
- 経営と介護現場の仲介
介護リーダーは、事業所によってチーフ・主任・リーダーなどの役職名になります。
業務内容は事業所によって異なるものがあるでしょうが、介護リーダーは介護現場の要であることには違いありません。
介護リーダーの求められる技術と能力については、こちらの記事をご覧ください。
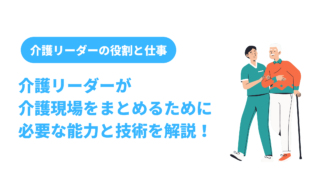
介護リーダーの業務内容

介護方針の決定
介護保険制度や法人理念にもある、利用者の自立支援・QOLの向上といった方針のもとで、私たちは仕事していますが、実際の現場ではもっと細かなレベルでの方針が必要になります。
自分たちの介護の方針を示していくことです。
- 右麻痺があり、自助具を使っているが半分くらい食べこぼしのある利用者の食事の自立支援について
- 尿意を訴えられない、座位保持が難しい利用者の排泄の自立支援について
こういったことを現場のスタッフから問われることがでてきます。
スタッフにも個々の考え方があり、仕事の仕方はその考え方に基づいて行われることが多いです。
- 右麻痺があっても左手で自助具を使い、食べこぼしがあっても自分の手で最後まで食べることが自立
- 右麻痺という機能障害があるから摂取動作には介助が必要で、何を食べたいかを聞いてそれを適えることが自立
- 他の人の介助も忙しいし、ちょっとでも自分で食べてくれるなら介助せずに自分で食べてもらったらいい
- 時間もないし、介助して早く食べてもらったら仕事が早く片付く
- 尿意を訴えられなくても、排泄の間隔を把握して座位を支えてトイレで排泄してもらうことが自立
- おむつ交換にするが、使用するオムツは尿量や体型、交換時間の間隔をもとに選定して、不快なく介助することが自立
- トイレで介助した方がいちいちベッドへ移乗しなくても済むから楽にできる
- 尿意がないなら、1日2回のおむつ交換でいい
これでは時と場合によって介助の方法がバラバラになります。
ここで介護リーダーの出番です。
「私たちの介護とは…」と、自分自身の言葉と行動で示していくことが求められます。
すぐに理解が得られ、スタッフ全員の行動が変わるわけではありません。リーダーが発信し続けていくことで、少しづつ現場に浸透していきます。
現場レベルで介護の方向性を浸透させていくためには、事あるごとに具体的に示し続けていくことがとても重要です。
スタッフの業務管理
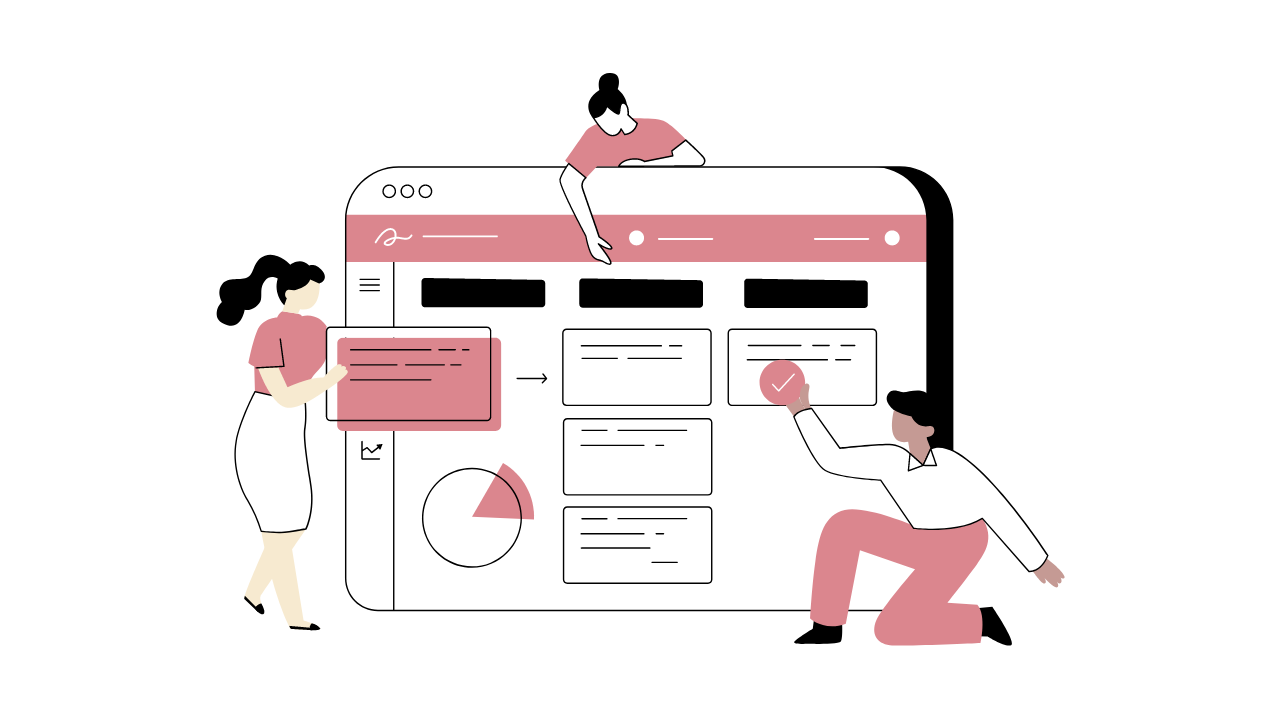
「意識や気持ちがあればできる!」
というものではありません。
意識や気持ち・思考は大切ですが、それだけでは無理なことをリーダーは認識しておかなければいけません。
人員の配置が合っていない・時間の割り振りが適切でない・介助に必要な物品が整っていない、など広い視点で要因を探る必要があります。
- 適切な人員配置で考えられたスタッフのシフト管理
- 利用者の快適さ、スタッフの働きやすさのための業務改善
リーダーの立場で、業務がスムーズに行えているかを見極める客観的な視点と課題に対して解決策を検討している姿勢が必要です。
適切な人員配置で考えられたスタッフのシフト管理
介護施設では早出や遅出などのシフト制で勤務しています。
介護職員が25名いても、早出・日勤・遅出・準夜・深夜など各勤務に分かれると2〜3名ずつになることが多いです。
事業所によっては「午前は人員が少なく、午後には余裕がある」とか、逆に「午前は余裕があるが、午後になると人員がいなくなる」などのばらつきも出てきます。
- 業務内容に合わせて人員配置を変える
- 人員配置に合わせた業務内容に変える
業務内容と人員配置をうまく考えようとすればこの方法になります。
人員が多くいる時間帯と、人員が少ない時間帯の業務内容を見直しましょう。
また、勤務できる曜日に制限があるスタッフもいます。「土日祝祭日は休み」の契約で勤務しているスタッフがいれば、必然と平日と土日祝祭日の勤務者に差が出てしまします。
シフト作成時に大きな差が出ないように勤務者を調整し、それでも調整がつかない場合にはその日の業務量を減らす(入浴者を変更するなど)工夫をしましょう。
利用者の快適さ、スタッフの働きやすさのための業務改善
利用者の暮らし方は私たちの業務(仕事)と密接に関わっています。
「8時から朝食」の場合、8時から食事が食べられるように食堂に集まってもらいますが、介助を要する利用者であれば、スタッフが順番に食事介助を行います。
例えば…
| 利用者数 | スタッフ数 | スタッフ1人に対する利用者数 |
| 75人 | 6人 | 12.5人 |
この場合、スタッフ1人で利用者12人の食事介助を対応することになります。最初に介助を受ける利用者と、最後に介助を受ける利用者とではかなりの時間差が生じることになります。
利用者を待たせることなく食事介助をするとなると、スタッフは焦ります。早く食事介助を終わらせて、次の介助をしようとします。
そうすると、スタッフは心理的な負荷を受けて一部介助を全介助にする、次々口に入れて誤嚥させてしまうなどを起こし、利用者の自立を阻害して命を危険にさらすことにつながりかねません。
スタッフの人員を考えると、時間差をなくすことは無理なので、どのように待ち時間を過ごしてもらうかを考えます。
- 食事介助が対応できる時間まで、居室で休んでもらう
- テレビや読書などができるスペースで待ってもらう
食堂でテーブルに食事を置いた状態で待ってもらうと、利用者とスタッフの双方に良い状態にはなりません。
| 要介助の利用者 | ・目の前に食事があると食べようと手を伸ばす ・目の前に食事があるのに食べられないことにストレスを感じる |
| 周りの利用者 | ・置いてある食事を食べようとする ・要介助の利用者に食べるように何度も声をかける |
| スタッフ | ・視界に入ると早く介助しなければと焦る ・待たせていることに申し訳なさを募らせる |
このような弊害に繋がってくると考えられます。
あらゆる日常生活の場面で、利用者の過ごしやすさとスタッフの仕事のしやすさにつながる業務の改善は、リーダーにとって重要な仕事といえます。
スタッフの育成

介護資格を持っているスタッフ、資格はないけど経験はあるスタッフ、資格も経験もないスタッフなど、色々なスタッフがいます。
しかし、同じように利用者の食事介助や排泄介助、また記録や行事などの企画、利用者のアセスメントなどの業務を行うことになります。
- 現場で活躍できるスタッフを育成する
- 次のリーダーを育成する
リーダーが行うスタッフの育成はこの2点になります。
現場で活躍できるスタッフを育成する
まずは、リーダーが示す介護方針を理解し、シフトに入り日々の業務を行う「現場のスタッフ」を育成することです。
入職時には付き添いながら利用者情報を伝え、また業務の手順を見本をみせながら指導したでしょうが、1人でシフトに入るようになってからは関わる機会も少なくなります。
介護技術においても、初めのことはゆっくり丁寧にしていた介助も、慣れてくるといい加減になる場合もあります。
利用者にとっても苦痛を伴う介助になり、スタッフにとっても介護技術が向上しないという結果になります。
本当にこの介護の方法でいいの?と振り返りの機会を、リーダーが意図してつくらなければいけません。
フタッフ本人に気づきを持ってもらい、自らが振り返るように導くことが大切です。
そのためには、シフトや業務に入らずとも現場に身を置いて、絶えずスタッフの言動にアンテナを張り、それぞれの良いところや改善を要するところを見極めるようにしましょう。
次のリーダーを育成する
自分がリーダーとして行なっている業務は、いつか誰かに引き継ぐ必要があります。
自分だけができればいい、自分だけがわかっていればいい、ではなく誰になっても必要なことは同じことができる状態をつくっておくことも、大事な業務の一つです。
- 業務の手順をマニュアル化する
- 書類、データ、情報は常に整理しておく
- リーダー業務をしている自分をまわりのスタッフに見せる
リーダーはシフト作成や、予定の組み立てなど、他のスタッフとは違う業務を行います。
シフト作成を例に挙げても、スタッフの組み合わせや夜勤明けは遅出にするとか、いつまでに作成して決裁を受けないといけない、など詳しいことはリーダーしかわからないこともあります。
そういった業務の手順や決まり事をマニュアル化しておきましょう。
そして、そのために必要な書類はファイルごとに見出しをつけて整理しておきましょう。
またデータもPCのファイルごとに分類して、データにはわかりやすい名前を入力して、常に整理しておきましょう。
見たい時に見たいものがすぐに手元に取り出せる、という状況をつくっておきましょう。
リーダーはいつどのようにしてリーダーの業務をしているのか、周りのスタッフは分かりません。まわりにスタッフがいる状況で、あえてリーダー業務を行い、この時にこのようにしてリーダーの仕事を行なっていることを、見える形で行動してみましょう。
自分の行動に明確な意図を持たせることで、周りのスタッフにも意図が伝わりやすくなります。
経営と介護現場の仲介
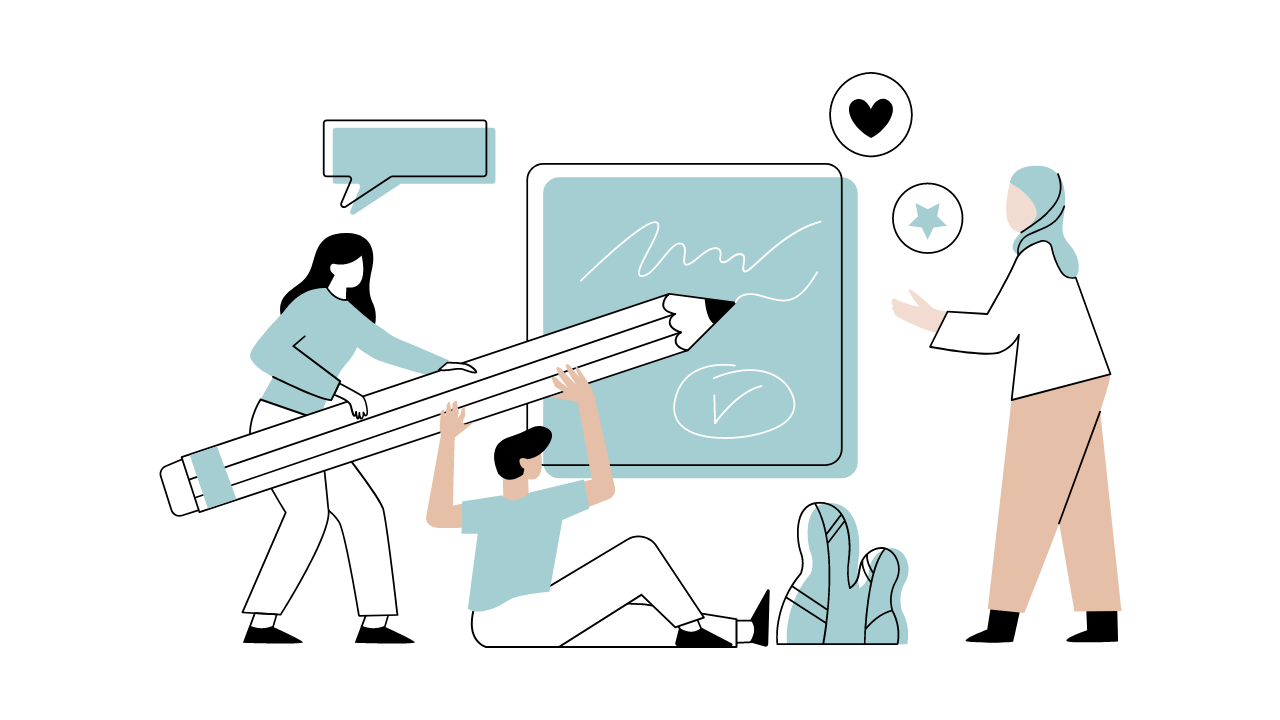
現場の介護リーダーは中間管理職に該当し、まさに経営陣と現場の間に位置する立場です。
経営陣からは、利用実績を上げろ、記録・提出物は早急に提出、人材育成をしっかりやれ、など上司から言われます。
現場からは、勤務が回らないからスタッフを増やしてほしい、休みが欲しい、人間関係に疲れた、など部下から言われます。
上と下からの板挟みです。流石にしんどさしか感じられない話になりますが、スタッフのため経営陣と対話できる立場は介護リーダーしかいませんし、経営の状況を現場スタッフにわかるように伝えられるのも介護リーダーしかいません。
会社にとっても経営側と現場側を仲介してくれる介護リーダーは、キーパーソンです。そして、その経験は介護リーダーのマネジメントの力を育ててくれます。
以下の書籍が介護リーダーの仕事についてわかりやすく解説してあります。漫画になっているのでとても読みやすく分かりやすく、おすすめの書籍です。
少し古くなりますが、実際の介護現場での物語を通して表したこちらの書籍もおすすめです。
まとめ
介護リーダーが担っている業務内容は以下のとおりです。
- 介護方針の決定
- 自分たちの介護方針を示していく
- スタッフの業務管理
- 適切な人員配置で考えられたスタッフのシフト管理
- 利用者の快適さ、スタッフの働きやすさのための業務改善
- スタッフの育成
- 現場で活躍できるスタッフを育成する
- 次のリーダーを育成する
- 経営と介護現場の仲介
- 経営側と介護現場の間に立つキーパーソンになる
苦労も多い介護リーダーですが、その経験は大きな力になることは間違いありませんし、自分の価値を高めることにも繋がります。
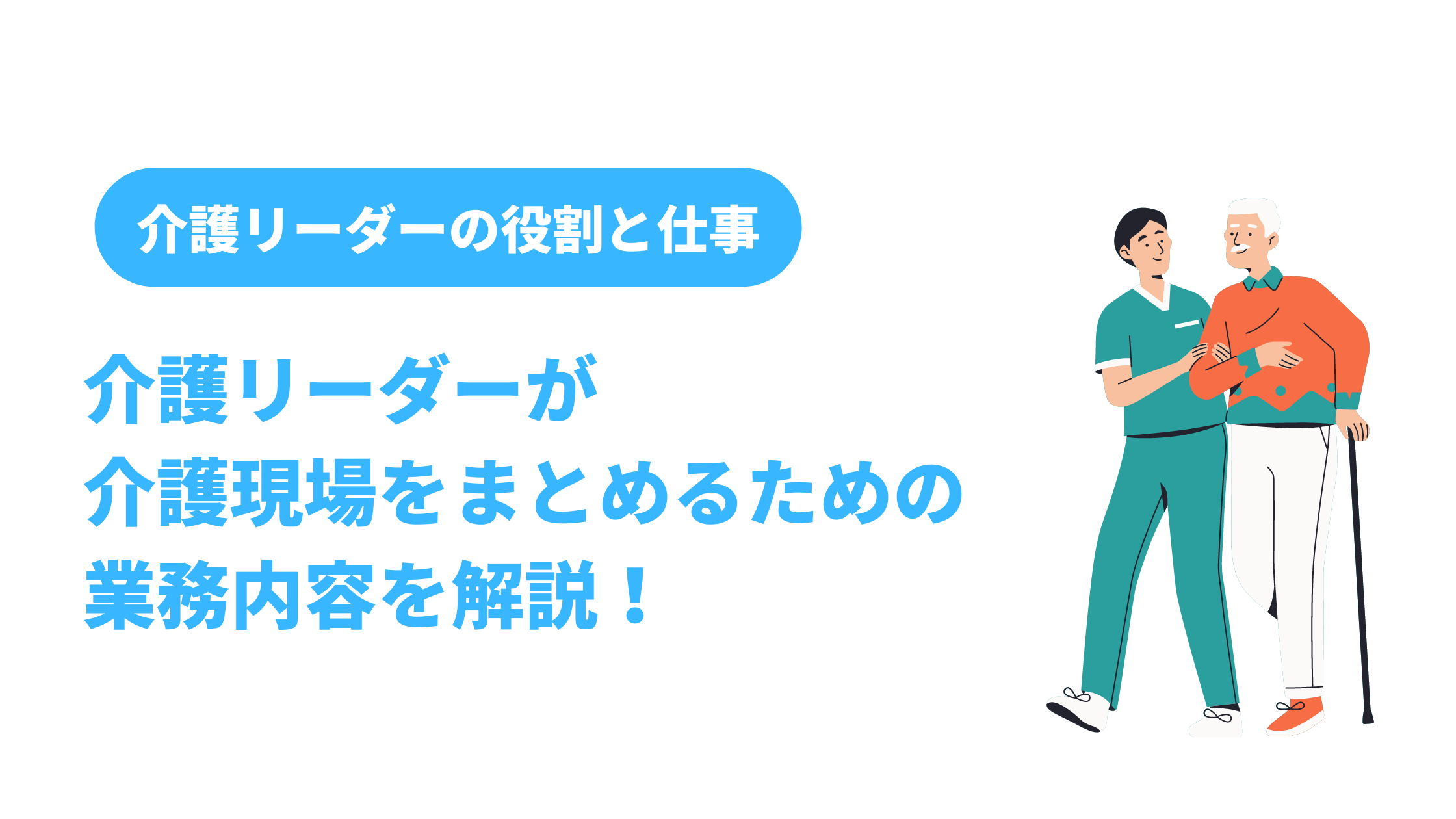


コメント